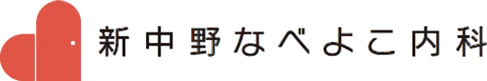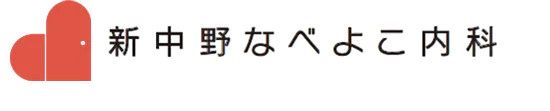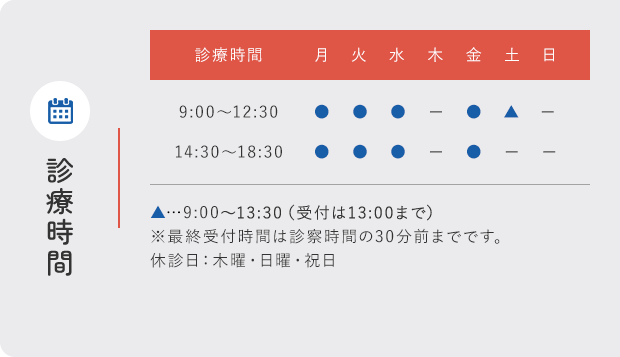突然の関節の激しい痛み、もしかすると「痛風」かもしれません。
痛風は、血液中の尿酸が高くなり関節に結晶がたまることで炎症を起こす病気です。激痛を伴う発作のほか、腎機能障害や尿路結石のリスクもあるため、放置せず適切な治療と生活管理が重要です。
当院では、中野エリアで痛風や高尿酸血症の早期診断・治療に力を入れています。痛風発作の対処から、再発予防のための尿酸管理・食事指導まで、総合的にサポートいたします。
痛風とは?
痛風は、血液中の尿酸が高くなることで、尿酸の結晶が関節にたまり、激しい痛みや炎症を引き起こす病気です。特に、足の親指の付け根に多く発症し、痛みは風が当たっても痛いほど強烈です。
発作が繰り返し発生すると、関節が破壊されたり、腎機能障害や尿路結石などのリスクが高まります。
そのため、痛風を放置せず、早期の治療と生活習慣の改善が重要です。
高尿酸血症と痛風の関係
高尿酸血症とは、血液中の尿酸値が7.0mg/dL以上になる状態を指します。この状態が進行すると、痛風発作を引き起こす原因となります。
尿酸が関節に結晶としてたまると、激しい炎症が発生し、強い痛みを伴います。
痛風は、突然の関節痛、赤く腫れて熱を持つという特徴的な症状が現れます。放置すると、関節や腎臓にダメージを与え、生活の質を大きく低下させる可能性があります。
痛風発作の特徴と症状
痛風の症状は、以下の特徴があります
・突然の激しい関節痛(主に片側)
・赤く腫れ、熱を持つ(炎症反応)
・足の親指の付け根に多く発症
・発作は3~7日間続くことが多く、再発を繰り返します
痛風は、特に30〜50代の男性に多く見られ、女性は閉経後にリスクが高まるとされています。
高尿酸血症を引き起こす原因
尿酸が高くなる原因としては、以下の要素が関与しています
尿酸の過剰産生
肉類や内臓、魚介類の過剰摂取、アルコール(特にビール・日本酒)などが原因になります。
尿酸の排泄低下
腎機能低下、脱水、糖尿病、加齢などが関与しています。
さらに、肥満やストレス、不眠なども尿酸値に影響を与え、痛風のリスクを高めます。これらのリスク要因が重なることで、尿酸値が高くなりやすくなります。
痛風の検査と診断
痛風を診断するためには、以下の検査が必要です
血液検査:尿酸値や炎症反応をチェックし、痛風発作が発生しているかを確認します。
尿酸値は痛風発作中には測定が難しいことがあるため、発作が落ち着いた後に管理を開始します。
また、腎機能や尿路結石のリスクを評価するために、必要に応じて尿検査や腹部エコー検査も行います。
痛風治療の流れ
1. 急性期(発作中)の治療
・NSAIDs(ロキソプロフェンなど)やコルヒチンを使用して炎症や痛みを軽減します。
・安静と患部の冷却が効果的です。
・血流を促すため、飲酒や入浴は控えるようにしましょう。
2. 尿酸値のコントロール
・発作が落ち着いた後、1〜2週間後から尿酸値を下げる薬を開始します。
・急激に尿酸値を下げることは再発の原因となるため、段階的に調整します。
3. 生活習慣の改善と薬物療法
・プリン体を控えたバランスの良い食事を心がけましょう。
・水分補給をしっかりと行い、1日2Lを目安に摂取します。
・アルコールは控えめに(特にビールや日本酒には注意が必要です)。
・運動や減量も尿酸値の安定に効果的です。
再発を防ぐための生活習慣
痛風の再発を防ぐためには、以下の生活習慣の改善が重要です:
・低プリン体食(野菜、果物、大豆製品を中心に)
・こまめな水分補給(特に就寝前や起床時)
・メタボリックシンドロームの予防(肥満やストレス管理)
・夏場の脱水予防(特に注意が必要です)
痛風でお悩みの方へ
痛風発作が繰り返す前に、早期の診断と治療が重要です。痛風を放置すると、関節の破壊や腎機能障害、尿路結石など、重大な合併症を引き起こすリスクがあります。
当院では、痛風の急性期治療から尿酸値の長期的な管理、食事や運動指導まで、一貫したサポートを提供しています。
気になる症状があれば、早めにご相談ください。健診で尿酸値が高いと言われた方も、ぜひ当院での診察をお勧めします。
よくある質問(Q&A)
Q1. 痛風は自然に治ることはありますか?
A. 発作は一時的に治まることがありますが、根本的な治療を行わないと再発を繰り返し、関節や腎臓にダメージが蓄積します。
Q2. どのタイミングで内科を受診すればよいですか?
A. 関節が突然腫れて痛みが出た場合は、すぐに受診してください。特に足の親指に多い発症パターンは典型例です。
Q3. 痛風になったらどんな薬を使うのですか?
A. 発作時には痛み止めや抗炎症薬を使用し、再発予防のためには尿酸を下げる薬を継続的に使用します。